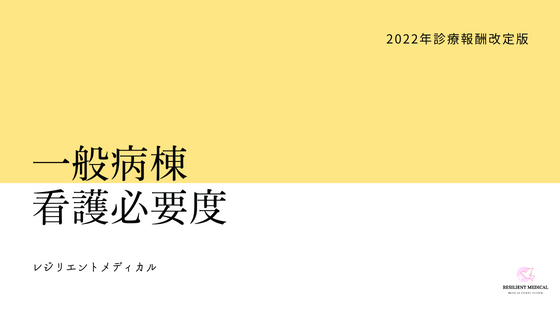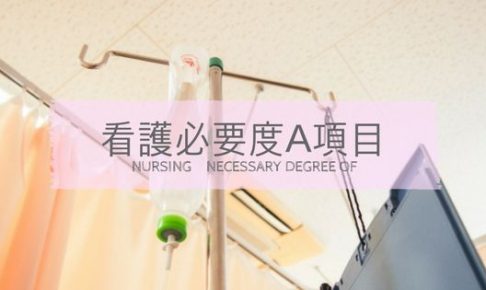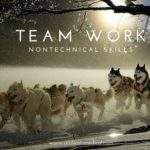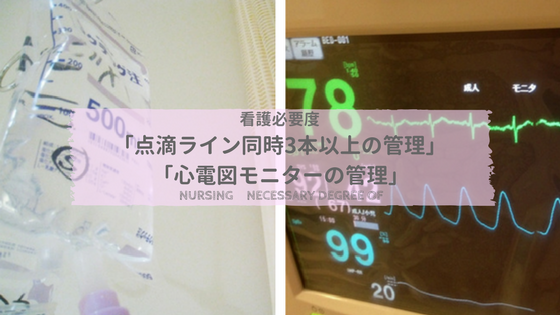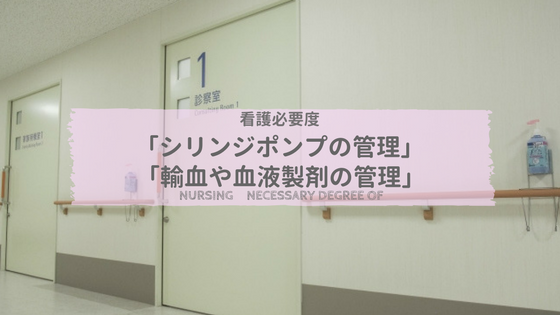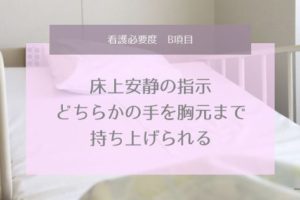目次
看護必要度 A項目 モニタリング及び処置等
A1 創傷処置
【定義】
①創傷の処置(褥瘡処置を除く)、②褥瘡の処置のいずれかを、看護師等が医師の介助を行った場合、あるいは看護師等が自ら実施した場合に評価する。
【判断基準】
「なし」 創傷処置を行わなかった場合
「あり」 創傷処置のいずれかを行った場合
【留意点】
創傷とは皮膚・粘膜の破綻を指し、縫合創は含めるが単純な穿刺創は除く。
気管切開口・胃瘻・ストーマ造設直後など抜糸までの処置や滲出がある場合は含む。
VAC療法、眼科手術後の点眼、ストーマ排泄物処理は含めない。
褥瘡はNPUAP分類Ⅱ度以上またはDESIGN-R2020 d2以上に該当した場合のみ対象。
A2 呼吸ケア(喀痰吸引を除く)
【定義】
酸素吸入、体位ドレナージ、スクウィージング、人工呼吸器の管理を看護師等が実施した場合に評価。
【判断基準】
「なし」 実施しなかった場合
「あり」 実施した場合
【留意点】
喀痰吸引のみは対象外。
NPPVは含めるが、エアウェイ挿入やネブライザーは含まない。
人工呼吸器は種類を問わず、装着状態や換気状況の確認を伴う必要がある。
A3 注射薬剤3種類以上の管理(2024年改定で本格運用)
【定義】
注射投与された薬剤が3種類以上であり、その管理を行った場合に評価。
【判断基準】
「なし」 薬剤が2種類以下
「あり」 薬剤が3種類以上
【留意点】
評価対象は「薬剤の種類数」であり、回数やルート数ではない。
同一成分名は1種類として数える。
血液代用剤・透析用剤・検査用剤など一部は対象外(コード表に準拠)。
食事療法の代替として投与されるビタミン剤は原則対象外。
A4 シリンジポンプの管理
【定義】
各ルートからの微量持続注入をシリンジポンプで行い、看護師等が投与量・投与時間を管理した場合に評価。
【留意点】
作動していない場合は対象外。
PCAは看護師等が持続投与を管理している場合のみ対象。
A5 輸血や血液製剤の管理
【定義】
輸血や血液製剤投与後に看護師等が管理を行った場合に評価。
【留意点】
種類や単位数は問わない。
腹膜透析・血液透析は対象外。自己血輸血や腹水濾過輸血は含む。
A6 専門的な治療・処置(2024年改定後整理)
【定義】
以下の処置を実施した場合に評価:
①抗悪性腫瘍剤(注射剤)
②抗悪性腫瘍剤の内服管理
③麻薬注射薬(注射剤)
④麻薬の内服・貼付・坐剤管理
⑤放射線治療
⑥免疫抑制剤の使用(注射・内服)
⑦昇圧剤の使用(注射剤)
⑧抗不整脈剤の使用(注射剤)
⑨抗血栓塞栓薬の持続点滴
⑩ドレナージの管理
A7 救急搬送後の入院(評価期間5日間に統一)
【定義】
救急車またはドクターヘリで搬送され、そのまま一般病棟に入院した場合に評価。
【留意点】
ICUや救命救急病棟を経由した場合は対象外。
手術室を経由して病棟に入院した場合は対象。
搬送当日を含め5日間を評価。
B項目(患者の状況等)
共通事項・定義は2022年と大きな変更なし。ただし、評価時の「自立度が低い方を採用」や「禁止動作を無断で行った場合はできるとする」等の運用は2024年改定でも継続。
例:
B8 寝返り
B9 移乗
B10 口腔清潔
B11 食事摂取
B12 衣服の着脱
B13 診療・療養上の指示が通じる
B14 危険行動
C項目(手術・医学的処置)
【改定のポイント】
2020年改定で延長された「評価日数」は2024年でも継続。
「別に定める検査」が拡充され、短期(2日)と長期(6日)が設定。
同一疾患による一連の再手術は初回のみ対象。
【対象手術・処置と評価期間】
C15 開頭手術:13日間
C16 開胸手術:12日間
C17 開腹手術:7日間
C18 骨の手術:11日間
C19 胸腔鏡・腹腔鏡手術:5日間
C20 全身麻酔・脊椎麻酔の手術:5日間
C21 救命等に係る内科的治療:5日間
C22 別に定める検査(短期):2日間
C23 別に定める検査(長期):6日間